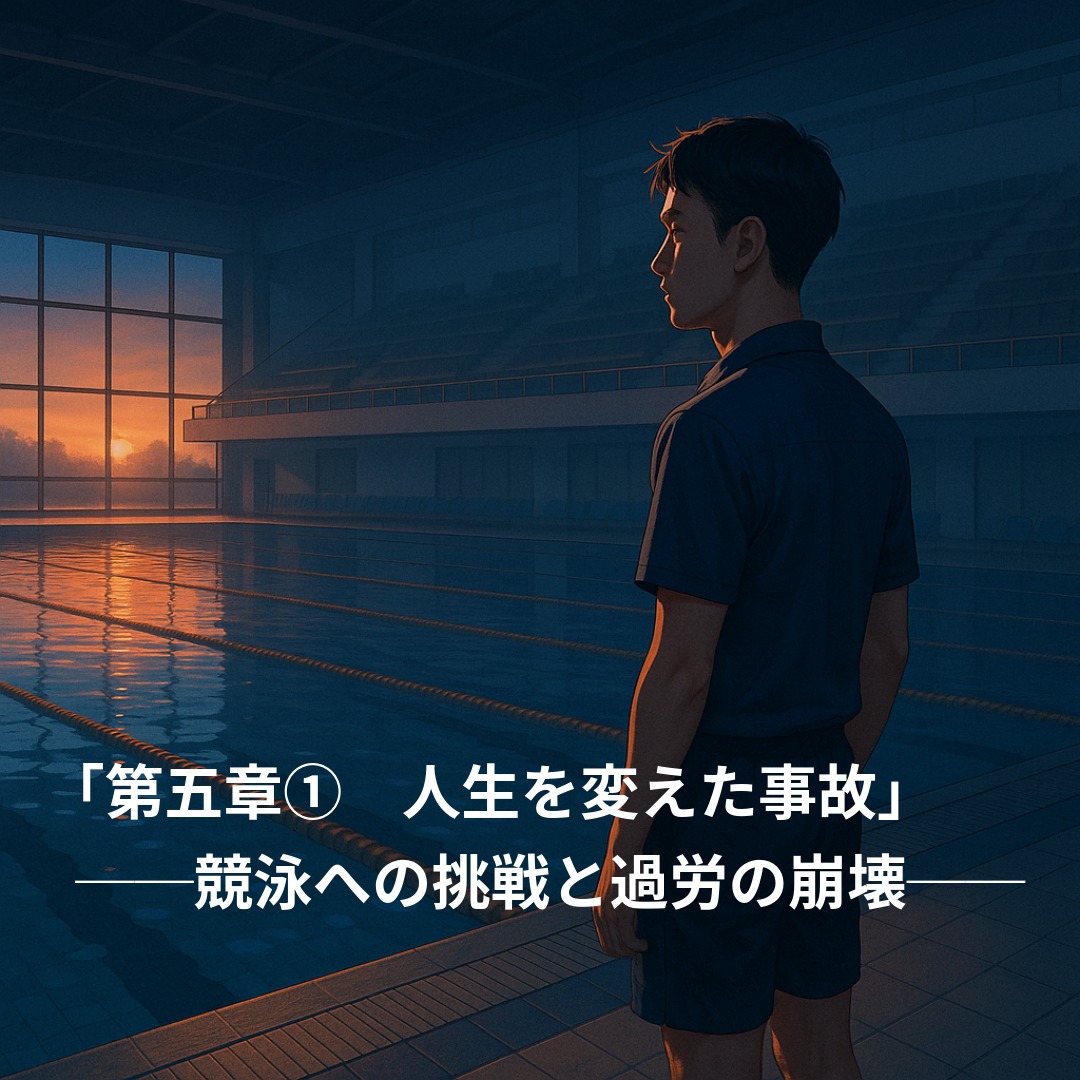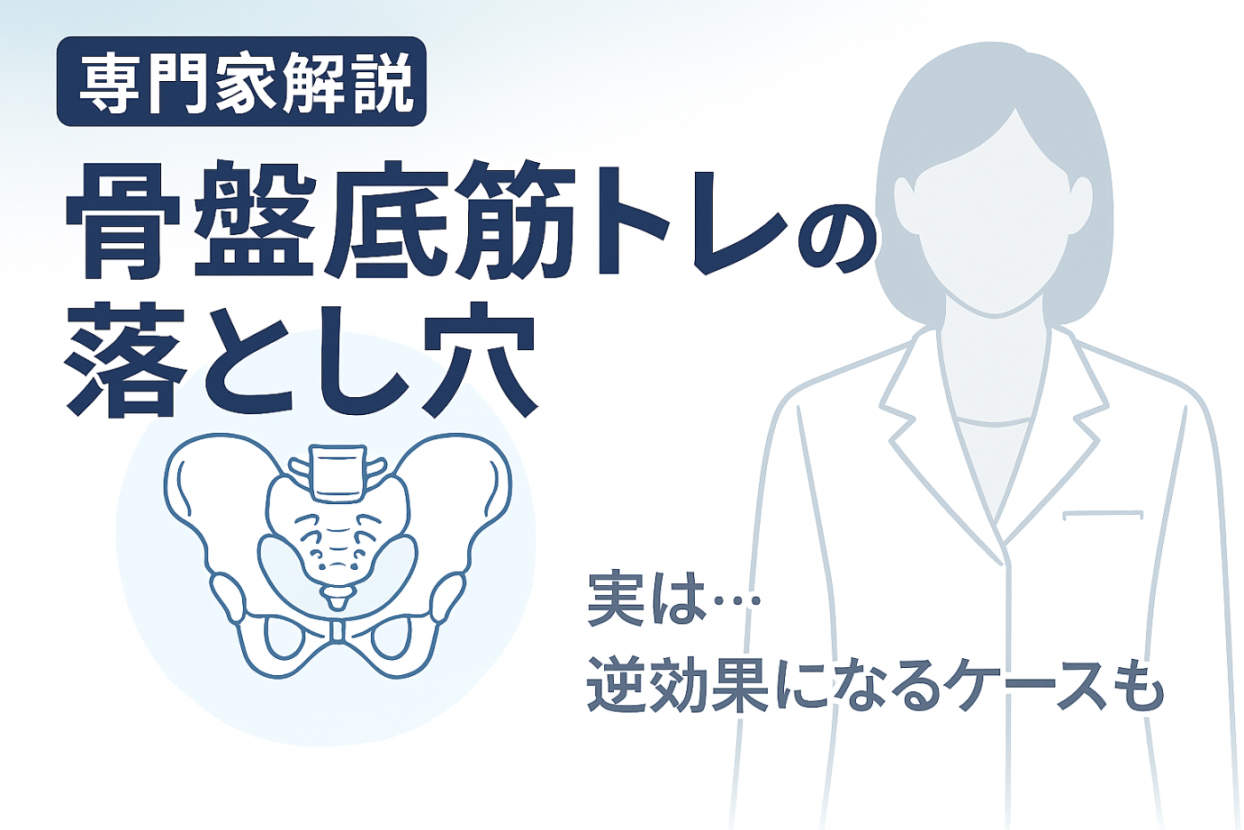ブログBLOG

筋膜の常識が覆る!専門家が語る、あなたが知らない5つの驚きの事実
最近、「筋膜リリース」や「筋膜はがし」といった言葉をよく耳にするようになりました。テレビや雑誌で特集が組まれ、多くの人が体の不調改善のために注目しています。あなたも「筋膜」という言葉に、なんとなく「全身を覆うボディスーツのようなもの」というイメージをお持ちかもしれません。
しかし、その実態は、私たちが想像するよりもずっと複雑で、生命の神秘に満ちた驚くべきシステムです。専門家が語る筋膜の本当の姿を知ると、これまでの体に対する見方が180度変わってしまうかもしれません。
今回は、専門家の解説に基づき、多くの人が知らない「筋膜」に関する5つの驚きの事実をご紹介します。あなたの体の常識が、ここから覆ります。
--------------------------------------------------------------------------------
1. "筋膜"は筋肉だけの膜じゃない。そもそも名前が誤解のもと?
まず、最も基本的な誤解から解いていきましょう。多くの人が「筋膜」という名前から、「筋肉を包んでいる膜」というイメージを持っています。もちろんそれは間違いではありませんが、全体像のほんの一部に過ぎません。
そもそも「筋膜」の語源であるラテン語の「fascia(ファッシャ)」には、「束」「包帯」「帯」「リボン」といった意味があります。古代ローマで権威の象徴とされた「ファスケス(Fasces)」という、斧の周りに木の束を結びつけたものがありますが、これは一本一本は弱くても束ねることで強くなるという考え方を示しています。筋膜の役割もこれと同じで、体の様々なパーツを「束ねて」「結びつけ」「強くする」ことにあるのです。
そして、その対象は筋肉だけではありません。筋膜は、神経、内臓、血管など、体の中のあらゆる組織を包み込み、支えています。この点について、専門家は次のように指摘しています。
筋膜って日本語に直しただけで実はその元々のファッシャっていう中に筋っていう意味は入ってないんで、ま訳した時ちょっとあまりうまい役じゃないんだな。
つまり、「筋膜」という日本語訳が、かえって私たちのイメージを「筋肉」だけに限定させてしまっていたのです。
--------------------------------------------------------------------------------
2. 実は「これが筋膜です」と誰も言えない?専門家も悩むその正体
驚くかもしれませんが、「これが骨です」と明確に示せるのとは違い、「これが筋膜です」と断言できる統一された定義は、実は存在しません。専門家の間でも意見が分かれており、それが筋膜という概念を少し分かりにくくしている一因でもあります。
この違いを理解するには、次のような対比が役立ちます。「骨であれば、指をさして『これが骨です』と言うのは簡単です。しかし筋膜の場合、『これが筋膜です』というよりは、腱を包む膜(腱膜)、筋肉の表面を覆う膜、神経を覆う膜といった、様々なものを全部寄せ集めたものが筋膜である」と専門家は説明します。
この曖昧さは今に始まったことではなく、1600年代から様々な定義が提唱され、議論が続いてきました。この状況を的確に表現したのが、イギリスの解剖学者スンドラーマンの言葉です。
筋膜は科学的に明確な解剖学的表現というよりかは一般総称的な表現である。
これは筋膜の欠点ではなく、むしろ体全体に広がり、あらゆるものを結びつけている筋膜という「システム」の複雑さそのものを表していると言えるでしょう。
--------------------------------------------------------------------------------
3. 体の硬さの原因はこれ?全身に広がる「網とドロドロ」の構造
では、私たちの体の動きや「硬さ」に直接関わる筋膜の構造は、どのようになっているのでしょうか。
筋肉と筋肉の間、あるいは組織と組織の間を覗いてみると、そこには驚くべき世界が広がっています。それは、コラーゲンの繊維でできた蜘蛛の巣のような「編みあみ」のネットと、ヒアルロン酸などを含んだ潤滑油のような「ドロドロ」の液体が組み合わさった構造です。
この「編みあみ」と「ドロドロ」のおかげで、私たちの体の各層はスムーズに滑り合い、自由な動きが可能になります。しかし、加齢や怪我、運動不足などによってこの「ドロドロ」の潤いが失われると、「編みあみ」の繊維同士がくっつき、滑りが悪くなってしまいます。これが、体の「硬さ」や動きにくさの正体の一つなのです。
これは単なる理論モデルではありません。実際に体内に内視鏡を入れて撮影した映像には、組織の間でキラキラと輝くこの網状の世界が映し出されており、私たちの滑らかな動きがいかに繊細な環境によって支えられているかを物語っています。そしてこの微細な構造こそが、次に紹介する体全体の繋がりを生み出す布地そのものなのです。
--------------------------------------------------------------------------------
4. 全ては繋がっている。足の裏から頭まで続く、一枚の連続した組織
解剖学の教科書を見ると、筋肉は一つひとつが独立したパーツのように描かれています。しかし、筋膜の視点から見ると、体はまったく違う姿を見せ始めます。
実際には、大胸筋が上腕の筋膜に直接入り込んでいたり、筋膜が骨を覆う骨膜(こつまく)に繋がり、その骨膜がまた別の組織に繋がっていたりと、体は文字通り頭のてっぺんから足の裏まで、一枚の連続した組織で繋がっているのです。
この全身の繋がりについて、専門家は力強くこう断言します。
全部体中全部全部繋がってます。
この状態を、映画『ホビット』に出てくる巨大な蜘蛛の巣に例えています。蜘蛛の巣の一本の糸を指で弾けば、その振動がウェブ全体に瞬時に伝わるように、私たちの体も同じです。体の一ヶ所に生じた緊張や動きは、この筋膜のネットワークを通じて、全身にあっという間に波紋のように広がっていくのです。
これが、腰が痛いのに足首を調整したり、肩こりの原因が腕にあったりする理由です。体は部分の集合体ではなく、すべてが影響し合う一つの統合されたネットワークなのです。
--------------------------------------------------------------------------------
5. 骨で体を支えていない?骨が「浮いている」テンセグリティ構造
最後に、最も衝撃的な事実かもしれません。私たちはこれまで、体は骨が積み木のように重なり合って支えられている「圧縮構造」だと考えてきました。しかし、最新の考え方は全く異なります。それが「テンセグリティモデル」です。
このモデルの革新的な点は、骨同士が直接お互いを支えているのではない、という考え方です。では、どうやって体は形を保っているのか?答えは、筋膜をはじめとする軟部組織が作り出す張力(テンション)の網の中に、骨が「浮いている」というのです。
専門家は、この構造をシンプルにこう表現します。
軟部組織、筋膜の中に骨が浮いてるってことです。
この構造のおかげで、私たちの体は驚くほどしなやかで、衝撃を一点に集中させず全身に分散させることができます。押しても元に戻る弾力性や、転んだ時のダメージ吸収能力は、このテンセグリティ構造がもたらす恩恵なのです。
--------------------------------------------------------------------------------
おわりに
いかがでしたか? 筋膜とは、単なる「筋肉を包む膜」ではなく、体中のあらゆるものを繋ぎ、動きの滑らかさを生み出し、さらには骨格構造そのものを成り立たせている、知的で連続的なシステムです。
今回ご紹介した5つの事実は、筋膜の世界のほんの入り口に過ぎません。最後に、あなたに一つ問いかけをさせてください。
「自分の体を一つの繋がった知的なウェブとして捉え直したとき、あなたの動きや姿勢、そして健康に対する考え方は、これからどう変わっていくでしょうか?」