|
前回の続き:気付き(アウェアネス)が身体を変える
今回は前回のお話「気付き(アウェアネス)が身体を変える」の続きです。
気付き(アウェアネス)が現れやすい人と表れにくい人がいます。
これにはいくつか理由が考えられますが、ざっくりいうと「集中力」が無い人はアウェアネスが現れにくいです。
「集中」と「執着」の違いとは?
ここで注意したいのが「集中」と「執着」が勘違いされているケースです。
なんのこっちゃ?という方が大半だと思うので、ある武道系YouTuberがとても良い説明をされていたので、それを参考に説明します。
武道家の言葉が教えてくれた本当の集中
その武道家の人は「集中と執着」を勘違いしている人が多いと言ってました。それはどういう事かと言うと…
「例えば、戦う相手がナイフを持っていたとして、ナイフにばかり注意がいってしまうのは“集中”ではなく、ナイフに対する“執着”であり、それは動きを固くしてしまう。」
「真の集中はその時その時の状況に合わせて、意識をフォーカスする場所を自由自在に出来る事で、動きは固くならずむしろ柔軟になる」
これを聞いた私は「おぉ!なんて素晴らしい説明!」と思いました。
執着=「居着き」=動きが止まる状態
この誤った集中…いわゆる執着は武道の世界では「居着き」と言って、動きが止まってしまう好ましくない状態なんですね。
この執着を集中と勘違いしている人がとても多いです。
「集中すると緊張する」という誤解
実は以前にあるスポーツ選手にボディワークを教えていて
「もっと集中してください」とアドバイスしたら
「集中すると緊張するじゃ無いですか?」と返されてしまって、正直言うと
あぁ、この人は集中を勘違いしているなと思いました。
「選択的注意」=アウェアネスを促す脳の機能
真の集中とは意識をフォーカスする対象を自由自在に出来る事です。
これを脳科学の世界では「選択的注意」と言います。
この選択的注意は「気付き(アウェアネス)」を促す事が科学的にも分かっています。
→ 高次脳機能とアウェアネス
選択的注意が弱いとどうなるか?
選択的注意とは外界から特定の情報(例:会話、作業)に焦点を当て、ノイズや無関係な刺激を無視する能力なので
選択的注意の能力が低下すると複数の刺激から必要な情報に集中できず、注意力が散漫になります。
具体例としては…
・マルチタスク(例:料理しながら電話)ができず、作業が混乱する
・雑踏の中で騒音が気になって会話に集中できない
・集中できないことへの苛立ちが増え、感情制御が難しくなる。
鍵は「前頭前野」そしてマインドフルネス瞑想
選択的注意の能力は脳の中では「前頭前野」という高次の脳で行っています。
言ってしまうと「前頭前野」の働きが低下すると武道でいうところの「居着く」状態になりやすい、つまり運動をする際に余計な緊張が生まれやすくなります。
前頭前野の働きを高める訓練として有名なのが「マインドフルネス瞑想」です。
みなさんも一度は聞いた事ある方も多いかもしれませんね。
マインドフル瞑想とは?
ヴィパサナ実践とマインドフルネスの関係
実は私はマインドフル瞑想のネタ元である「ヴィパサナ実践」をスリランカの高僧であるアルボムッレ・スマナサーラ長老を始めとした、修行僧の方に真剣に教わっていた時期がありました。
アルボムッレ・スマナサーラ氏は養老孟子先生とも対談本を出されたり、ビル・ゲイツなどの有名なセレブしかスピーカーになれないプレゼンショー「TED」でもスピーチ経験がある、とても有名な僧侶です。
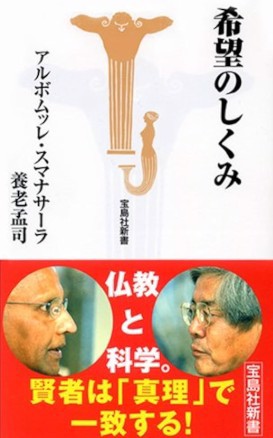
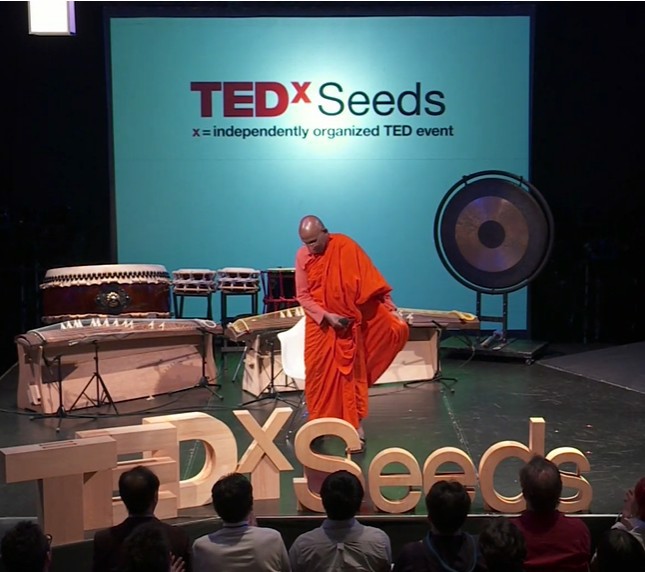
ヴィパサナ実践?何それ?と思った方は、逆にマインドフル瞑想をWikipediaなどで調べると良いです。
マインドフル瞑想の創始者のジョン・カバットジンは元々ヴィパサナの指導者で、難度の高いヴィパサナを一般にも普及したいと思ってマインドフル瞑想を作ったのです。
その辺りの経緯は以下のダライ・ラマの書籍に書いています。
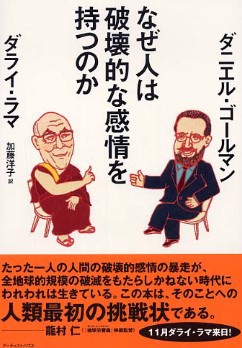
瞑想とは「今、この瞬間以外を手放す」こと
いわゆる「マインドフルネス瞑想」を調べると「今この瞬間に意識に向ける」と説明されている事が多いかと思います。
これは簡単に言うと「今この瞬間以外を手放せ」と言う事です。
瞑想と言うとみなさん第一声で「座禅して無になる事を目指すんでしょ?」と返ってくる事が多いです。
実はそれこそが妄想です(笑)
雑念に気付くこと=集中力を高める訓練
今この瞬間以外を手放すと言う事は、それこそ執着を手放すと言う事です。
マインドフル瞑想のような事をしているとあれやこれやと雑念が湧いてきます。
・足が痛くなってきたな
・あぁ、今日の晩御飯なんだったっけ
・超能力が見に着くかな?
・きちんとできているかな?
・つまんないなぁ…
無になりたい=結果に執着している状態
言ってしまうと「無にならなくちゃ」というのも雑念です。
「無になりたい」などの雑念が沸く人は「結果を得たい」と言う気持ちが大きすぎる人です。
こういう雑念は「今この瞬間」に気付く能力の邪魔をします。
成功も失敗も、いったん横に置く
極端な事を言うと…成功するか、失敗するか、も無視して
とにかく、今の瞬間に徹底的に集中するのが重要なんです。
科学的にも証明されたマインドフルネスの効果
何で重要なの?と気になる人は多いでしょうが
回答としては「やれば分かる」が本当の正解です。
しかし、それでは納得しないのが現代人(笑)
一応、エビデンスを無理やり作るならばマインドフルネス瞑想の継続的な実践は脳科学的には前頭前野の機能を高めます。
それは先ほど伝えたように「選択的注意」の能力が向上します。
また、DMN(デフォルトモードネットワーク)という「注意散漫」などと関係する部分を軽減する効果が科学的に認められています。
Brewer, J. A., et al. (2011). "Meditation experience is associated with decreased default mode network activity and connectivity." Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(50), 20254–20259. doi: 10.1073/pnas.1112029108
ヴィパサナの「順番」とボディワークの共通点
実はヴィパサナには順番があります。
それは初心者は「身体の観察」から「心の観察」へと移るという順番です。
実は身体の動きを観察するヴィパサナもあります。
禅ではそれを「歩行禅」と呼びます。
実は身体の観察の方が簡単なんです。
なので初心者は本当は歩行禅から始めます。
でも、日本人はミーハーなので坐禅が好きなんでしょうね。
体験会など言っても坐禅しか教わらないと思いますが、坐禅は基本的に難しいです。
実は豆知識ですが…ヨガのアーサナ(ポーズ)も初心者の為のもので、最終的には「ラージャヨガ(坐禅)」へと進む為のウォーミングUPです。
しかし坐禅も歩行禅もやってる事は同じで「今この瞬間に集中する」と言う事です。
実は当院のボディワークも同じ構造です
そろそろ勘が良い人は気付いてきたと思いますが、実はボディワークにも「ヴィパサナ」の要素が入っています。
これはボディワークの歴史を詳しく知れば当たり前の事なんです。
当院の体操(ボディワーク)にもヴィパサナと同じような効果があると言う事です。
とういう事で、当院のボディワークも実施する時には「今この瞬間」に徹底的に集中するように実践してみてください!
・あと何回やるのかな?
・これで正しく出来てるのかな?
・どんな効果があるのかな?
・つまらない、飽きてきたな
・どの筋肉をつかうのかな?
などの考えが浮かんで来ても、すぐに執着を捨て今この瞬間の身体の感覚に集中してください!
身体の感覚に繰り返し集中していると余計な思考が生まれなくなっていきます。
そうすると真の集中力がじわじわと表れて最大限の効果が出ます。
もちろん、そう出来なくとも効果は出る内容になってますけどね
ですが余計な雑念を捨て、今この瞬間に「全集中」すればきっと皆さんが「想像していた以上」に、感動する程の効果が出ます!
先日はダンサーの女性の方が自分では既に出来ていると思っていた体操を、今の身体の感覚に「全集中」で実施した後にこれまでと全く違う効果が出て驚いていました。
また、男性のサラリーマンの方でついつい頑張ってしまう人で効果が出なかった方が「全集中」して実施したら、全くワーク中の身体の使い方が変わってお互いに驚いた事があります。
このような感動体験をもっとたくさん生み出せるよう指導者の私もより良い指導方法の探索に頑張らなくてはいけません。
「偏桃体」の働きを抑える瞑想の力
また、ヴィパサナやマインドフル瞑想には「偏桃体」と言って不安や恐怖と強く関係する脳の部位の活動が低下させる効果があります。
https://www.jneurosci.org/content/23/13/5627
それがストレスを軽減させると言われる所以なんですね。
だから、私は時々ですが「体操をするとぐっすり眠れるようになりますよ」とお客様に言っています。
あと、コラム完成直前にしたのような論文も発見したので貼っておきます。
瞑想と言うと神秘的に感じたり、非科学的なオカルトに感じるかも知れませんが、基本的に当院では科学的な根拠をベースに人間の運動を語ります。
今回のコラム同様でなるべく「引用文献・論文」を記載するようにしておりますので、安心してお越しに下さいね(笑)
|


