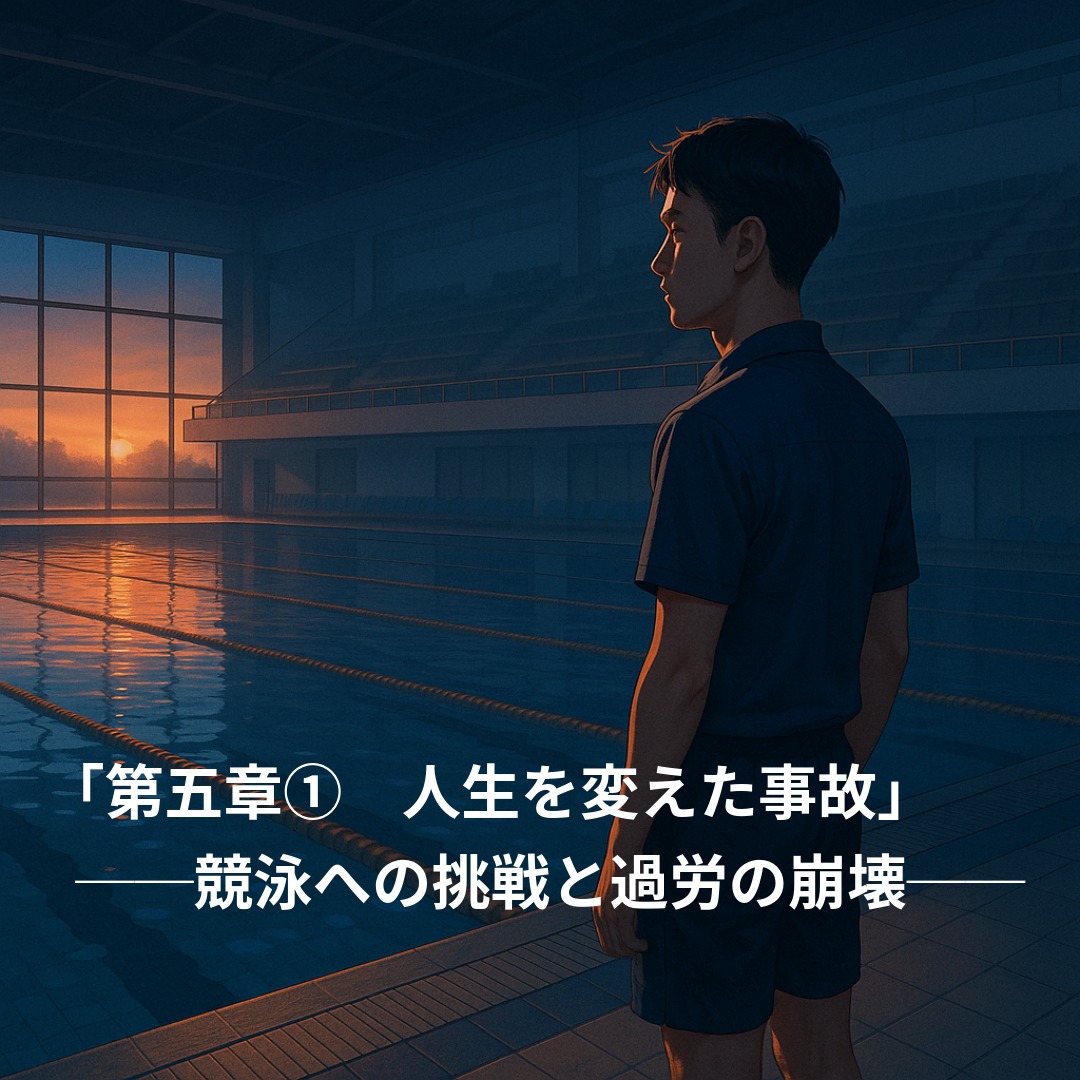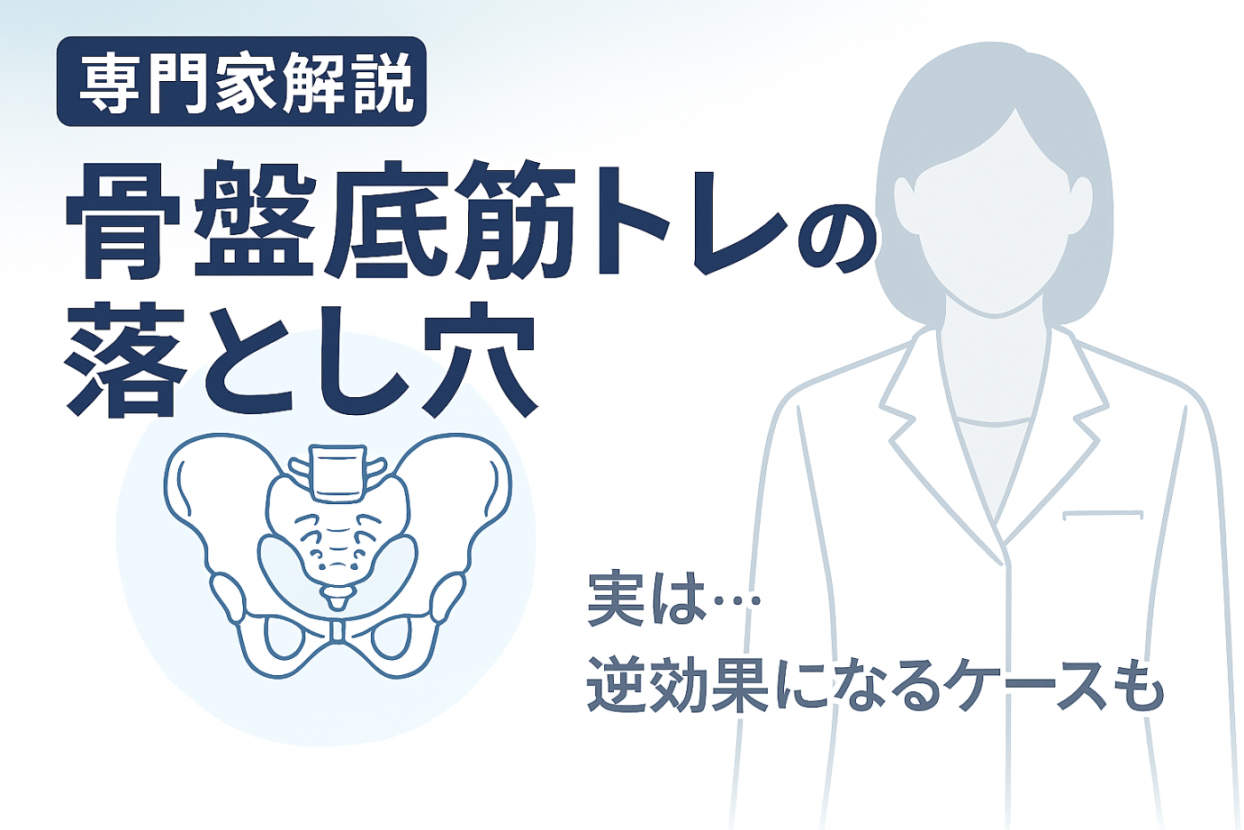ブログBLOG

個人が個人を裁くという危険性──理性と法が人類に与えたもの
ある国で、思想の違いから著名人が命を奪われる事件があった。
この出来事はニュースやSNSで拡散され、立場の違う人々の間でさまざまな反応を呼んでいる。
中には「当然だ」「仕方ない」という声すらある。
しかし私はここに、人類が繰り返してきた危険な罠を見る。
正義は立場によって変わる
人は誰もが、自分の立場から「正義」を語る。
しかし、その正義は別の立場から見れば「悪」となる。
だからこそ、戦争はなくならない。
科学はこの問いに答えを与えられない。
「正義」が本当に普遍的に存在するのかどうか、実証はできないのだ。
だから人類は、終わりのない報復を避けるために「法」という仕組みをつくった。
感情のままに個人が裁きを下すのではなく、第三者の調停によって争いを制御する。
それが文明の基盤になった。
宗教と経験の知恵
仏教の十戒には「生き物を殺さない」という戒律がある。
これは単なる道徳ではなく、「殺せば必ず悪い結果が返る」という長い人類の経験知の結晶だと、私が学んだスリランカの僧侶は語った。
東洋医学も同じ構造を持っている。
科学的な証明がなくとも、「この行為は良い結果をもたらす」という統計的な積み重ねの上に体系が築かれている。
つまり、宗教も医学も、方向は違えど「人間が生き延びるために守るべき行為」を集めてきたのだ。
哲学と政治からの視点
ハーバード大学のサンデル教授は『これからの「正義」の話をしよう』の中で、学生たちにこう問う。
「人を殺すことは、正義となり得るのか?」
議論は簡単に答えを出さない。
しかし浮かび上がるのは、立場によって正義が変わる以上、個人が感情で裁きを下すのは危険だ ということだ。
だからこそ近代社会は、法を整備し、暴力を独占し、個人の復讐を禁じる方向に進んできた。
政治思想の違いではなく、これは人類が生き延びるための必然だったのだ。
人間の進化が与えたもの
もちろん、人を殺したいほど憎む気持ちは人間にある。
それを否定することはできない。
だが人間は進化の中で、理性によって本能を制御する能力を手に入れた。
もし誰もが怒りのままに殺し合えば、復讐の連鎖で世界はすぐに滅ぶだろう。
理性は人間らしさそのものであり、法はその理性を社会的に制度化したものだ。
だから私はこう考える。
どんなに強い憎しみがあっても、個人が個人を裁いてはならない。
それが人類が数千年かけてたどり着いた知恵であり、私たちが守るべき最低限の理性だからだ。